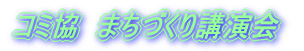
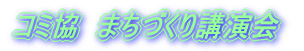
|
皆さんは裁判員制度をご存知ですか! 裁判員という耳慣れない言葉、そして選ばれたら裁判に参加するという現実、今まで裁判所とか、 裁判官・・・など、どちらかといえば、テレビや新聞で見聞きする位の事でしかなかったのに、どう して一般の人が裁判員になったり、裁判に参加しなくてはいけないの・・?と驚かされたり心配した りするかもしれません。 そこでコミ協では、平成十九年度まちづくりの一環として一月二十七日、増林地区センターで埼玉 地方検察庁の増田検務官をお招きして講演会を開催しました。 |
|||||||||
開会に先立ち講師紹介をする石崎会長 |
平成19年度 まちづくり講演会 日時 平成20年1月27日(日) 14時〜16時 会場 増林地区センター多目的ホール 講師 埼玉地方検察庁 増田 検務官 |
||||||||
|
|||||||||
|
裁判員の選ばれ方 | |||||||||
|
参加者からは、裁判員制度が身近に感じられ、当事者になった場合の質問が寄せられ、限られた時間で説明 対象となる事件は
裁判員制度について詳細は、裁判所が公表している
「裁判員制度トップページ」をクリックして参照してください。
|
|||||||||